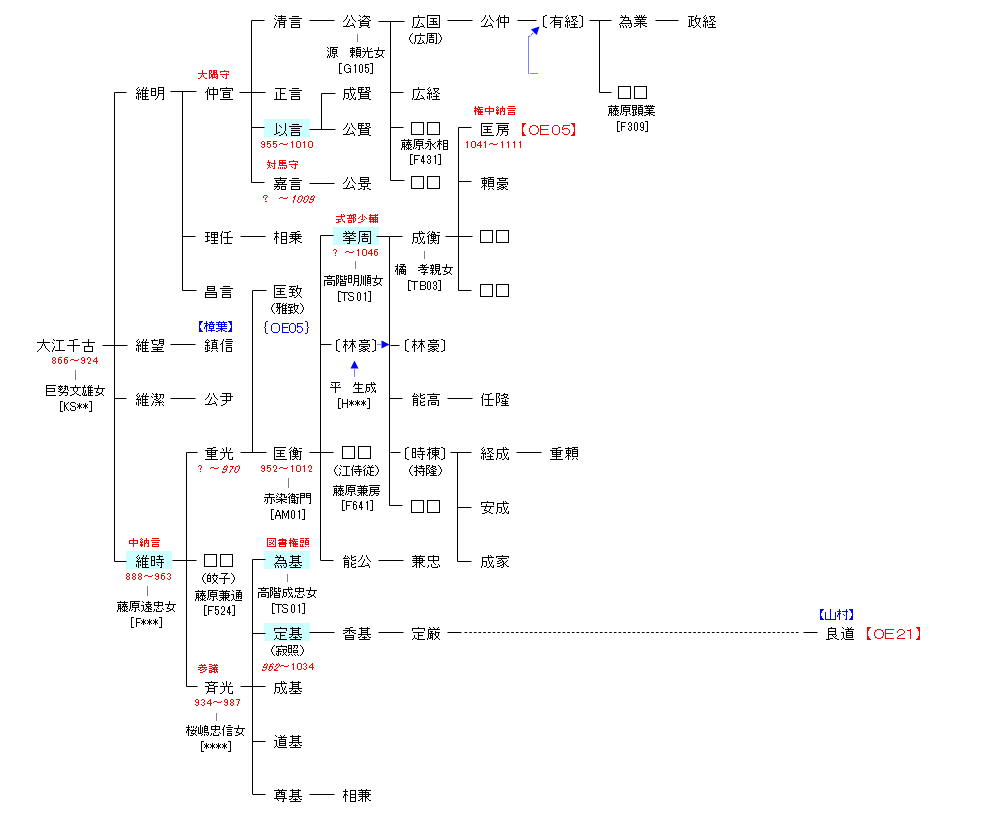|
漢学を藤原篤茂に学んだ。正六位上文章得業生から身を起こし、長保3年(1001年)8月従五位上、長保から寛弘年間にかけて文章博士を勤め、治部少輔を経て、従四位下式部権大輔に至った。
世に「帥殿方人」と目されるほど藤原伊周(帥殿)と極めて親しく、そのため、伊周が失脚した長徳の変後、長徳2年(996年)10月10日の除目で飛騨権守に左遷された。その後も官途においては不遇で、「恨暗漢雲之子細」の佳句が一条天皇の知るところとなり、蔵人に補任されそうになったが、左大臣・道長と殿上人達が承引しなかったため、ことは立ち消えになった。憤懣やるかたない以言は、帝が奸臣に欺瞞されたことを風刺した詩句「鷹鳩不変三春眼、鹿馬可迷二世情」を放言した。それでも殿上人は「湯気の上らんとす」と以言の旧姓「弓削」をもじって皮肉ったという。ただし、道長が以言の漢詩を評価していたのも事実のようで、道長の『御堂関白記』には大江匡衡とともに以言をたびたび自らの詩会に招いている。
寛弘7年(1010年)7月24日、同年はじめに薨去した伊周の後を追うようにして卒去した。
ほかに源俊賢,藤原行成,具平親王との親交も詩作からうかがえる。その文体は自由奔放で新奇な趣向が目立つが、言い換えれば恣意で法則を無視したものが多く、とても後学には真似することができないと大江匡房に評されている。その秀作に対して、慶滋保胤が妬みにも似た感嘆を発したことがある。慶滋保胤はまた、具平親王の問いに対して、以言の詩文は「白砂の庭前、翠松の陰の下、陵王を奏するが如し」清奇であると評した。具平親王からも以言は詩文において「上手」と賞賛された。以言は同時代の高名な文士である紀斉名の詩を批判したことがあり、自らも文才を自負していた様子がうかがえる。
一条朝詩壇の詞華集である『本朝麗藻』の入集数は20首で、二位の具平親王(18首)を抜いて最多入集を果たしている。『和漢朗詠集』(11首)、『本朝文粋』(27首)、『新撰朗詠集』(35首)、『和漢兼作集』(6首)などにも詩文を採られている。『以言集』8帖、『以言序』1帖があったことが平安末期を生きた藤原通憲(信西)の蔵書目録に見えるが、伝わらない。
『江談抄』には彼の詩文にまつわる逸話が多く収められている。
|
大江氏の血だけでなく、祖父大江音人の門弟であった巨勢文雄を外祖父に持ち、早くからその才能を発揮した文章生になったのは29歳であったが、僅か1年でその上の文章得業生に選ばれている。
延喜21年(921年)に醍醐天皇の六位蔵人に任じられているが、その在任中から侍読も務め、延長6年(928年)に蔵人の労が評価されて叙爵を受けている。天暦4年(950年)に参議に列すると、天暦9年(955年)に従三位に叙せられ、天徳4年(960年)には73歳で中納言に昇った。
学者としても名が高く、大学助,文章博士,大学頭を歴任して、醍醐天皇,朱雀天皇,村上天皇の侍読を務め、「三代の侍読」と称された。『日観集』,『千載佳句』を編集。また、唐に留学して中国の兵法『三略』を学び、それを『訓閲集』という120巻の書物に記している。また、日本最古の兵書といわれる『闘戦経』の作者に比定されている。
記憶力に優れ、平安遷都以降の他人の死没年や屋敷の移り変わりの様子なども把握していたとされる。
従兄弟の大江朝綱とはライバル同士であったが、朝綱の子孫である大江匡房が著した『江談抄』(第5-51)には「維時は才学においては朝綱よりも優れていたが、文章においては朝綱の敵ではなかった」と評している。実際、『本朝文粋』に採録された当時の権力者・藤原忠平の文書の草案は全て朝綱によるもので、維時の文書は存在しない。
村上天皇の時代、内裏の屏風を飾る漢詩を大江朝綱,橘直幹,菅原文時の3人に作らせ、維時に選定させた。この時、菅原文時は黄帝が「洞庭」の地で楽を開いた故事を詩にして傑作を書き上げたが、維時は「文時は洞庭湖の詩を読んでいるが、黄帝が楽を始めたのは呉の洞庭(太湖に浮かぶ山)である」と指摘して酷評した。結局、他の詩は採用されたものの、文時はこの時の屈辱を死の間際まで恨んだと言う。
|