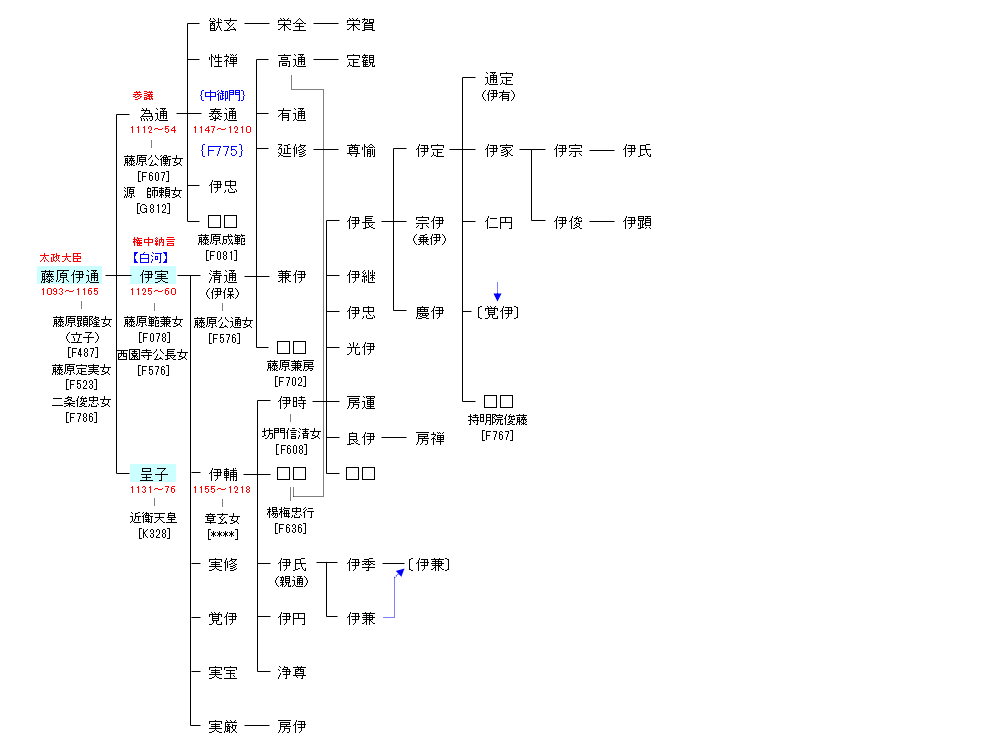|
九条に邸宅を構えていたことから九条大相国あるいは大宮大相国と号した。天永3年(1122年)に参議昇進。しかし、大治5年(1130年)10月、自身より後から参議になった藤原長実が先に権中納言に昇進したことを不満として籠居。天承元年(1131年)に官職(参議,中宮権大夫,右兵衛督)を止められる。長承2年(1133年)、朝政に復帰し、権中納言に進む。
その後、関白・藤原忠通に接近し、久安6年(1150年)に娘の呈子を忠通の養女として近衛天皇に入内させる。さらに近衛天皇の母・藤原得子(美福門院)や忠通らの信頼を得て発言力を強め、二条天皇の永暦元年(1160年)には、従兄弟の藤原宗輔の後を受けて正二位太政大臣に昇進、以後、死去の年まで5年に渡って在任した。朝政のあり方を説いた『大槐秘抄』を著して二条天皇に献じたことでも知られ、これを受けた天皇も関白・忠通とともに伊通を重用し、親政指向を強めて後白河院と対立した。
伊通にとって、美福門院は母方の従兄弟姉妹であり、また忠通は妹の婿で、彼の出世の背景にはこうした閨閥の力も無縁ではなかった。しかし、その一方で自身の豊かな才覚による政治力もあり、また詩歌・管絃・書にも通じた文化人で、機知に富んだ話術で常に宮中の人々を笑いを誘ったことなどが伝わる。さまざまな意味で同時代における第一級の宮廷人だった。また、先例を重んじつつも、道理に合わないと考えれば、それに拘らない柔軟性も有していた。
また、激しい性格で毒舌家でもあった。平治元年(1159年)の平治の乱後に藤原信頼が勝手に行った論功行賞で武士を厚遇するのを見て、「人を多く殺した者が恩賞に与るのであれば、どうして三条殿の井戸に官位が与えられないのか」と公言した。また、『大槐秘抄』では旧儀の復興を説く一方で、貴族や寺社に与えられるべき封戸の制度が廃れたために代わりになるものとして荘園や知行国の制度が存在していることを説いて荘園整理令を批判している。
日記に『九条相国記』(『権大納言伊通卿記』)がある。伏見宮御記録所収『白檀御仏御自筆法華経供養部類記』『本朝世紀』『御遊抄』などに、大治5年(1125年),保延元年(1135年)・2年,久安2年(1145年)・3年・4年・5年の記文がある。また、『九条相国除目抄』という除目に関する全8巻の書物を著していることが知られている(『本朝書籍目録』)。同書は現存していないが、『魚魯愚鈔』『除目抄』などに見える「九抄」「要抄」と記されたものがそれであると考えられている。
父である藤原宗通が死去する直前、「所領は一旦妻(伊通ら兄弟の母)に与え、妻が亡くなった後に子供達に分け与える」として、将来子供たちが受け取るべき土地を予め指定してから亡くなった。ところが、兄弟の1人である藤原信通が母に先だって病死した。そのため、母は死の直前に遺された他の息子で信通が与えられる筈だった所領を分けるように指示した。だが、伊通だけは「それでは父との約束に反することになる」と述べて亡兄の息子にその分を与えた。人々は彼を孝友廉直であると評した。
大治4年(1129年)の除目において、中原師遠を壱岐守と周防権守に二重に任じるミスがあったことが翌年になって発覚し、秋の除目にて取消の手続をしようとしたところ、師遠が病死してしまった。そのため、その扱いについて議論になった。その際に大外記は「(二重となってしまった)周防権守を取り消すのが妥当である」と述べたが、多くの貴族が死者に関わりたくないとそのまま空席にすればいいと主張した。だが、伊通のみは大外記が言う通りで公式記録にあってはならない記録が残ってしまうから、先例が無くても取り消すべきであると最後まで主張したが通らなかった。この件や『九条相国除目抄』の編纂などによって伊通が外記の業務に理解を示したことは外記局から長く感謝され、50年余り後に大外記の清原頼業が九条兼実に対して外記の立て直しに尽くした人物として藤原頼長,信西と並んで伊通の名前を挙げている。
伊通は自分が疑問に思ったこと、不審に思ったことは必ず、上臈や経験者にその場で質問して納得しようとする性格であった。その一方で、そそっかしい側面もあり、勘違いによる失敗談も伝えられている。
|
『古今著聞集』に藤原伊実の逸話が伝えられている。彼はもともと相撲や競馬などの武芸を好み、学問にはほとんど関心を示さなかったという。父の伊通はたびたびこれを叱責したが、伊実は改めようとしなかった。当時、「腹くじり」と称される相撲取りがいた。この力士は必殺技として相手の腹に頭を突き入れ、必ず転倒させることに長けていたため、その異名を得ていた。
伊通は密かにこの力士を召し出し、「我が子・伊実が相撲に耽るのは不本意である。もし彼を転倒させれば褒美を取らせるが、失敗すれば命はないと思え」と命じた。さらに伊実には「お前が相撲に執着するなら、この『腹くじり』と勝負せよ。勝てば以後咎めぬが、負けたら永久に相撲を禁ずる」と宣告した。
勝負の最中、伊実は最初こそ相手の攻撃を許したが、「腹くじり」が得意技を繰り出した瞬間、その四肢を掴み前方へ強く引き倒した。力士は首の骨が軋むほどの衝撃を受け、地面に叩きつけられた。策略が瓦解した伊通は不快の色を隠さず、「腹くじり」は行方をくらましてしまった。以降、伊実の相撲修業を阻む者はいなくなったという。
『古今著聞集』は説話集としての性質上、文学的脚色の可能性を排除できないものの、この逸話のみに注目すれば、伊実は当時の上層公家貴族の中で極めて特異な存在であったと言える。彼が相撲比試で収めた勝利は、単なる力の優位性を示すだけでなく、「柔よく剛を制す」と評されるような、相手の力を逆用して制する戦術的知性を立証している。
|